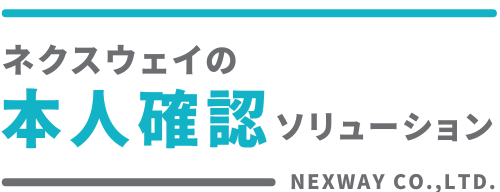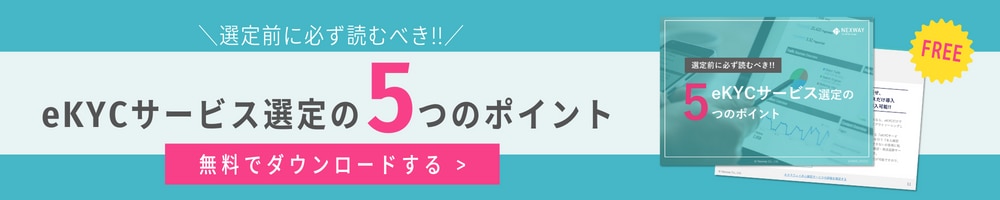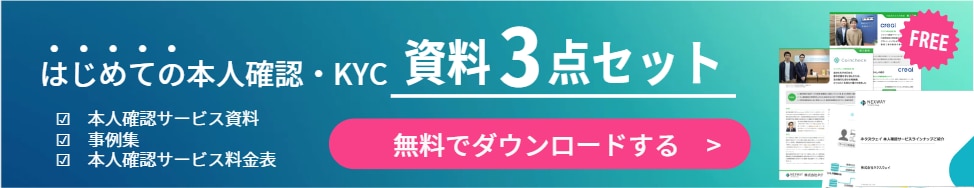【2026年4月改正予定】携帯電話不正利用防止法とは?本人確認要件とeKYC手法3つを解説!

eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード
eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は
本人確認ソリューションの導入事例をダウンロード
携帯音声通信事業者には、「携帯電話不正利用防止法」に基づき、契約者の本人確認が義務付けられています。
本人確認の実施には手間やコストがかかるため、意図せず適切ではない方法で済ませてしまうケースもあるかもしれません。しかし、同法の要件を満たさない確認を行った場合、違反とみなされ罰則が科される可能性があるため、十分な注意が必要です。
本記事では、携帯電話不正利用防止法の概要と、2026年4月に予定されている改正内容について詳しく解説します。あわせて、同法に準拠しながら本人確認業務の負担を軽減できる「eKYC」の活用方法についてもご紹介します。
目次[非表示]
- 1.「携帯電話不正利用防止法」とは?
- 1.1.「携帯電話不正利用防止法」の概要
- 1.2.規制の対象となるのは?
- 1.3.「SIMカード」のみの登録も対象
- 1.4.携帯電話不正利用防止法が制定された背景
- 2.【2026年4月施行】改正法の内容
- 2.1.主な改正ポイント
- 2.2.改正により変更される本人確認方法
- 2.3.改正に伴う対応策
- 3.携帯電話不正利用防止法で定められた本人確認手続きの方法
- 3.1.1対面手続きの場合
- 3.2.2非対面手続きの場合
- 3.3.本人確認記録の作成・保存までが義務の範囲内
- 4.携帯電話不正利用防止法に違反した場合の罰則
- 5.非対面で安全・手軽に本人確認するなら「eKYC」
- 6.携帯電話不正利用防止法に準拠した主なeKYCの手法
- 7.eKYCによって不正利用・なりすましを防ぐ!
- 8.まとめ
「携帯電話不正利用防止法」とは?

携帯電話不正利用防止法は、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」の正式名称です。
ここでは、法の概要や規制対象、制定された背景について解説します。
「携帯電話不正利用防止法」の概要
携帯電話不正利用防止法は、契約者の身元が確認されていない携帯電話が振り込め詐欺などの犯罪に悪用されていた問題を受け、2006年4月に施行されました。
2008年の改正では、SIMカードの無断譲渡の禁止や、レンタル携帯電話業者への本人確認義務の強化などが盛り込まれました。さらに2026年4月には、オンライン本人確認の厳格化を含む改正が予定されています。
スマートフォンの普及に伴い、大容量通信を売りにして新規参入する事業者が増加する中、この法律が適用される範囲も広がっています。携帯音声通信事業者は、法律を正しく理解していないと、思わぬ罰則を受ける可能性もあるため注意が必要です。
参考:e-Gov法令検索「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」
規制の対象となるのは?
携帯電話不正利用防止法の規制対象になるのは、MVNOを含むすべての通信事業者です。
MVNO(Mobile Virtual Network Operator)とは、ドコモやソフトバンク、auなどの通信キャリアから通信回線を借り受けて携帯電話やSIMカードなどの移動体通信サービスを提供する事業者を指します。月額料金が比較的安価であることから一般的には「格安SIM」とも呼称されます。
前述した通信キャリアやMVNO以外にも、契約代理業者や販売代理店、レンタル携帯電話事業者も規制の対象となります。
「SIMカード」のみの登録も対象
SIMカードのみの登録であっても携帯電話不正利用防止法は適用され、契約者の本人確認が必要です。MVNOでは、SIMカードのみの取り扱いをしている事業者もあります。
通信回線が3G以上である現在の携帯電話・スマートフォンの多くは、SIMカードを交換するだけで別名義で利用できます。このため、例えば通信本体が盗難物であっても簡単に転売・再利用ができてしまうため、SIMカードのみの登録でも確認が必要になります。
携帯電話不正利用防止法が制定された背景
携帯電話不正利用防止法が制定された背景には、一時期大きな問題となった「オレオレ詐欺」などの振り込め詐欺や、携帯電話の転売などがありました。特にプリペイド携帯などは、使用者の名義がわからなくても利用できるため、便利な一方で犯罪に使われる例が多くみられ、社会問題となっていたのです。
このような問題を受けて、新規契約だけでなく、携帯端末を譲渡する際にも本人確認を義務付けることで、携帯電話を利用した犯罪の抑止を目的に制定されました。
携帯電話を利用した犯罪について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
有効な転売対策14選を解説!対策の事例や転売による影響も紹介
eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード
eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は
本人確認ソリューションの導入事例をダウンロード
【2026年4月施行】改正法の内容

携帯電話不正利用防止法は2026年4月に改正が予定されていますが、その目的は本人確認書類の写しを用いる方法を廃止し、オンラインでの本人確認を厳格化することです。従来よりも精度の高い本人確認を義務付けることで、不正契約やなりすましを防止します。
ここでは、改正法の内容を解説します。
主な改正ポイント
改正での主なポイントは、次のとおりです。
1、現携帯法の「ハ方式」が廃止されます。この方式は顔写真撮影に加えて、マイナンバーカードや運転免許証など写真付き本人確認書類を撮影する方法です。
近年では本人確認書類の偽造が高度化しており、撮影画像の真偽を確認することが難しくなっているため、今回の改正でこの方法は廃止される予定です。
2、現携帯法の「ヘ方式」が廃止されます。この方式はWebサイトなどで本人確認に必要な書類の撮影画像(写し)をアップロードし、書類記載の住所に転送不要郵便などを送付する方法です。
アップロード前に画像の偽造などが行われる可能性があり1、と同様に撮影画像の真偽を確認することが難しくなっているため、今回の改正でこの方法も廃止される予定です。
3、非対面での顔写真のない書類送付が原則禁止されます。この方式は顔写真のない本人確認書類を送付し、書類記載の住所に転送不要郵便などを送付する方法です。送付書類の偽造・改ざんが行われる可能性を考慮し、原則禁止となりますが、住民票の写し(原本)など、偽造・改ざん対策が施された一部書類のみ引き続き利用可能となる予定です。
これらの改正により、従来の「本人確認書類の写しを用いる方法」は廃止され、今後はマイナンバーカードのICチップを読み取る方法が主流になる見込みです。
改正により変更される本人確認方法
今回の改正により、本人確認は方式ごとに次のように変更される予定です。
規定 | 改正前 | 改正後 |
ハ | 書類の画像+容貌(廃止予定) | IC チップ読み取り+容貌 |
ニ | IC チップ読み取り+容貌 | IC チップ読み取り+転送不要郵便等 |
ホ | 原本+転送不要郵便等 | 原本+転送不要郵便等 |
ヘ | 写し+転送不要郵便等(廃止予定) | 特定事項伝達型本人限定受取郵便等 |
ト | 特定事項伝達型本人限定受取郵便等 | 電子署名に係る電子証明書 |
チ | 電子署名に係る電子証明書 | 本人確認書類+転送不要郵便等 |
リ | ー | 写し+転送不要郵便等 |
表のとおり、大幅な変更が予定されているため、本人確認を実施している企業は改正に合わせて実施方法を変更する必要があります。今から改正に対する準備を進めておく必要があるでしょう。
参考:総務省「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集」
改正に伴う対応策
改正により「ハ方式」「へ方式」が廃止されると、Webサイト上だけで本人確認を完了できなくなり、別の方式への移行が必要となります。
オンラインでの非対面本人確認に利用できるのは、改正後の「ハ」「ニ」「ト」の方式です。これらの方式では、ICチップの読み取りが必須となるため、2025年4月時点では、スマートフォンのネイティブアプリの利用が前提となる可能性が高いと考えられます。
eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード
eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は
本人確認ソリューションの導入事例をダウンロード
携帯電話不正利用防止法で定められた本人確認手続きの方法

携帯電話不正利用防止法にならって正しく本人確認をするために必要なものは、契約者の以下の情報です。
なお、法人の場合には法人名称と所在地の確認が必要です。
では、実際に本人確認手続きをどのように実施すればよいのでしょうか。携帯電話不正利用防止法における本人確認の方法については、所管官庁である総務省が具体的な手法を提示しています。
これらについて、合計8つの手法が定義されています。次に、それぞれを詳しく解説いたします。
1対面手続きの場合
店頭で契約するなど、対面での手続きをする場合は次の2つの方法があります。
本人確認書類は、基本的に第三者が入手できない書類として運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどが該当します。
その他、第三者が入手できないものではないものの本人確認書類として認められるものに住民票のコピーまたは記載事項証明書、戸籍謄本または抄本などがあります。
2非対面手続きの場合
インターネットや電話など非対面での契約の場合、現行法の本人確認は次の6つの方法があります。
このうち、2026年の改正で「ハ」と「へ」の方式が廃止される予定です。
「手法ト」における特定事項伝達型本人限定受取郵便では、郵便物の受け取りに写真付きの本人確認書類が必要になります。
本人確認記録の作成・保存までが義務の範囲内
通信事業者は、本人確認を行ったあと速やかに本人確認記録を作成しなければなりません。いつまでにという指定は法律上特にありませんが、唯一レンタル携帯事業者に関しては3日以内に作成しなければならないという規定があります。
また、本人確認記録は契約終了後3年間の保存義務があります。本人確認記録に記載するのは、次の項目です。
本人確認実施日は、対面であれば本人確認書類の提示を受けた日です。非対面で本人確認書類のコピーを受けた場合では、契約者に契約書あるいは携帯本体が到着した日に該当します。
また本人確認記録は必ずしも紙面による必要はなく、データとして作成・保存しておくことも可能です。
eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード
eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は
本人確認ソリューションの導入事例をダウンロード
携帯電話不正利用防止法に違反した場合の罰則

携帯電話不正利用防止法に違反した場合、罰則として2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処されることになります。
実際に2021年、大手通信事業者のソフトバンク株式会社が契約者の本人確認を携帯電話不正利用防止法に則った形式で行わなかったとして、総務省から是正命令を受けています。
利用者が虚偽の氏名等で申告をすることも違反に
携帯電話不正利用防止法は、事業者だけでなくユーザーにも適用されます。ユーザーが契約の際、虚偽の氏名・住所・生年月日で申告することも違反となり、50万円以下の罰則を科される可能性があります。
また他人の名義で契約を行う行為や、契約した携帯電話を携帯電話会社に無断で第三者へ譲渡することも、同様に法律違反となります。
携帯電話不正利用防止法の違反事例
事業者が携帯電話不正利用防止法に違反した事例の一部を紹介いたします。
この中でもよくみられる違反は、法的な要件を満たさない本人確認を行っていたという事例です。本人確認業務にはコストがかかり、社内のコア業務に影響が出ることもあるため、負担を少なくしようとした結果、要件を満たさず違反になるというケースがあります。
レンタル携帯電話事業者の場合は、違反があった際には行政指導を経ることなく、直接罰則が科される可能性があります。また、携帯音声通信事業者には、販売代理店などの媒介業者が契約を行う際に、本人確認を確実に実施するよう監督する責任が課せられています。
eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード
eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は
本人確認ソリューションの導入事例をダウンロード
非対面で安全・手軽に本人確認するなら「eKYC」

通信事業に限らず、さまざまなサービスで契約手続きをオンライン上で完結させるケースが増えています。携帯電話不正利用防止法に準拠した本人確認も、安全かつ手軽に行いたい場合は、オンライン本人確認「eKYC」の導入が有効です。
eKYCとは、スマホやパソコンのカメラ機能を利用し、オンライン上で本人確認が完結するシステムです。はじめは金融機関やクレジットカード会社などで導入が進められていましたが、現在ではリサイクルショップやマッチングサービス、不動産業など多方面に渡って採用されています。
eKYCについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
eKYCとは?オンライン本人確認とKYCの違いや導入するメリットを解説
犯収法の要件を満たしたオンライン本人確認
eKYCは、犯罪収益移転防止法(犯収法)の要件を満たした本人確認手法です。犯収法とは、金融機関などの特定事業者に対して取引を行う際に本人確認を義務としている法律です。2018年の改定によって、オンラインでの本人確認が認められました。
eKYCは、スマホひとつで本人確認が完結する手軽さに加え、法律に準拠したシステムとしての高い安全性も備えています。
犯罪収益移転防止法についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
犯罪収益移転防止法とは?概要や本人確認(eKYC)の要件について
eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード
eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は
本人確認ソリューションの導入事例をダウンロード
携帯電話不正利用防止法に準拠した主なeKYCの手法

eKYCは犯収法に準拠しているというのは前述の通りですが、携帯電話不正利用防止法で求められる本人確認にも次のとおりの方法で対応しています。
携帯電話不正利用防止法における | 方法 |
現行「ハ」(廃止予定) | 顔写真付きの身分証+容貌撮影 |
現行「ニ」(「ハ方式」に変更予定) | 身分証のICチップ情報読み取り+容貌撮影 |
現行「チ」(「ト方式」に変更予定) | マイナンバーカード「公的個人認証サービス」の利用 |
「ニ」(新設予定) | 身分証のICチップ情報読み取り+転送不要郵便等 |
それぞれの方式について解説します。
顔写真付きの身分証+容貌撮影
本人確認書類として運転免許証などの顔写真付きの身分証と容貌を、事業者が提供したソフトウェアから撮影して送信を受ける方法です。これは、現行の携帯電話不正利用防止法における本人確認手法(ハ)に準拠します。
身分証は原本であることを証明するために、送信を受けるのは表面・裏面だけでなく厚みもわかるように撮影されます。また、なりすまし等を防ぐために送信を受ける画像は契約の際にリアルタイムで撮影されたものとし、端末の画像フォルダなどに保存された画像は使用できません。
ただし、このような顔写真のある本人確認書類を撮影した画像の送信を受ける本人確認方法は、精巧に偽造された書類が悪用されている実態があり、2026年の改正で廃止される予定です。
身分証のICチップ情報読み取り+容貌撮影
事業者が提供したソフトウェアから運転免許証やマイナンバーカードのICチップ情報を読み取り、合わせて契約時に撮影された容貌画像の送付を受ける方法です。これは、携帯電話不正利用防止法における本人確認手法(ニ)に準拠します。2026年の改正では、「ハ」方式となる予定です。
格納されたICチップ情報を展開する際には、PINコード(パスワード)が必要になります。
マイナンバーカード「公的個人認証サービス」の利用
マイナンバーカードのICチップを読み取り、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)が提供する公的個人認証サービスを使用する方法です。これは、携帯電話不正利用防止法における本人確認手法(チ)に準拠しており、2026年の改正では「ト」方式となる予定です。
利用者のマイナンバーカードに、あらかじめ電子証明書が付与されている必要があります。
JPKI(公的個人認証サービス)についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
JPKI(公的個人認証サービス)とは?マイナンバーカードによる認証の仕組みやワ方式の要件を解説
身分証のICチップ情報読み取り+転送不要郵便等
2026年の改正により、「ニ」方式として新たに導入される予定の方式です。事業者が提供するソフトウェアを通じて、運転免許証やマイナンバーカードのICチップ情報を読み取ります。
ICチップから取得した情報と申込者の入力内容を照合することで、なりすましの防止にもつながります。さらに、取得した住所に「転送不要扱い」の郵便物を送付することで、本人が実際にその住所に居住しているかどうかを確認する仕組みです。
eKYCによって不正利用・なりすましを防ぐ!

eKYCは本人確認がオンライン上ですべて完結するため、対面での本人確認と比較して、セキュリティや安全性に対して不安を感じるかもしれません。
しかしeKYCには高精度の画像認識技術が使われており、本人確認書類や容貌画像の偽造は困難です。仮に画像チェックをすり抜けたとしても、その後に行われるスタッフによる目視での書類・申込内容の突合で、不正は見抜かれる可能性が高いといえます。
eKYCではこのような厳しいチェックによって、不正利用やなりすましをしっかりと防止しています。
eKYC導入なら「ネクスウェイの本人確認ソリューション」がおすすめ
本人確認業務には、対面・非対面に関わらず手間がかかります。人件費や郵送費、印刷費などのコスト負担も小さくありません。また、本人確認記録を紙面で残している場合は保管場所の確保といった問題も生まれるでしょう。
このような課題を解決できるのがeKYCです。ただし、eKYCを提供するサービスの内容は多種多様であり、どれを選べばよいか迷われている事業者様・担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
eKYCの導入を検討中であれば、「ネクスウェイの本人確認ソリューション」をおすすめします。
オンライン本人確認から、その後の書類突合における目視確認、さらにオンラインでの本人確認が難しかった利用者への限定郵便の送付対応までを一括して委託できる、ワンストップ型のサービスです。世界最高水準のセキュリティと画像判定技術により、安心・安全な本人確認を実現します。また、使いやすいUIにより、本人確認の途中離脱を最小限に抑えます。「ネクスウェイの本人確認ソリューション」は、金融機関をはじめとした300社以上で選ばれているeKYCサービスです。
まとめ

携帯電話不正利用防止法は、携帯電話の不正利用や転売を防ぐために制定された法律です。この法律では携帯電話事業者に対して利用者の本人確認を義務付けており、確認方法が法令に沿っていない、または不十分な場合には罰則が科される可能性があるため、注意が必要です。
2026年には、オンラインでの本人確認手続きの厳格化を目的とした法改正が予定されています。記事で紹介した改正の内容は今後変更される可能性もありますが、現在公表されている改正案は、偽造による被害の増加という背景を踏まえ、施行される可能性が高いと見込まれます。常に最新の情報を確認し、早めの対応を心がけましょう。
eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード
eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は
本人確認ソリューションの導入事例をダウンロード