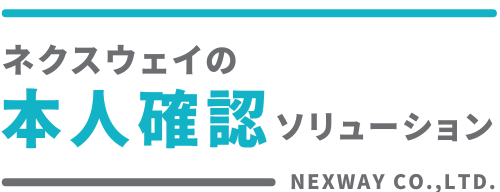JPKI(公的個人認証サービス)とは?マイナンバーカードによる認証の仕組みやワ方式の要件を解説
マイナンバーカードを使用した公的個人認証/JPKI(ワ方式)にも対応!
eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード
マイナンバーカード(IC認証)の導入方法を知りたい方は
マイナンバーカード(IC認証)導入完全ガイドをダウンロード
マイナンバーカードは、従来は行政手続きで活用されていましたが、近年は普及率向上や政府による民間利用の推進もあり、JPKI(公的個人認証サービス)を導入する企業が増えています。本記事では、JPKI(公的個人認証サービス)の概要やeKYC(オンライン本人確認)との関係、民間事業者がJPKIを導入する方法を解説します。
目次[非表示]
- 1.JPKI(公的個人認証サービス)とは?
- 2.JPKI(公的個人認証サービス)導入が進む理由
- 2.1.国が推奨し、民間利用が進むJPKI(公的個人認証サービス)
- 2.2.マイナンバーカードの普及で需要が高まっている
- 2.3.公的個人認証サービスの機能が拡充された
- 2.4.なりすましや身分証偽造ビジネスが横行している
- 3.JPKI(公的個人認証サービス)を利用するメリット
- 3.1.目視チェック不要で事務コストを削減
- 3.2.電子証明書による高い秘匿性
- 3.3.ユーザーの利便性を高める
- 4.JPKIで利用する電子証明書とは
- 4.1.マイナンバーカードには2種類の電子証明書が記載されている
- 4.2.電子署名との違い
- 4.3.電子証明書の注意点
- 4.3.1.利用者は暗証番号を覚える必要がある
- 4.3.2.電子証明書には有効期限が存在する
- 5.民間事業者がJPKI(公的個人認証サービス)を導入する方法
- 5.1.認定事業者になる
- 5.2.認定事業者に署名検証業務を委託する
- 6.公的個人認証/JPKI(ワ方式)を使った認証方法
- 7.ネクスウェイが考える現時点の本人確認の最適解
- 8.JPKIを活用する「ワ」方式も提供するネクスウェイの本人確認ソリューション
- 8.1.「ワ」方式以外の手法も利用できる
- 8.2.従量課金制のためコストを抑えられる
- 8.3.さまざまなシーンで利用されている
- 8.3.1.クレジットカードの発行時
- 8.3.2.マッチングサービスの登録時
- 8.3.3.決済サービスの申込時
- 9.まとめ
JPKI(公的個人認証サービス)とは?
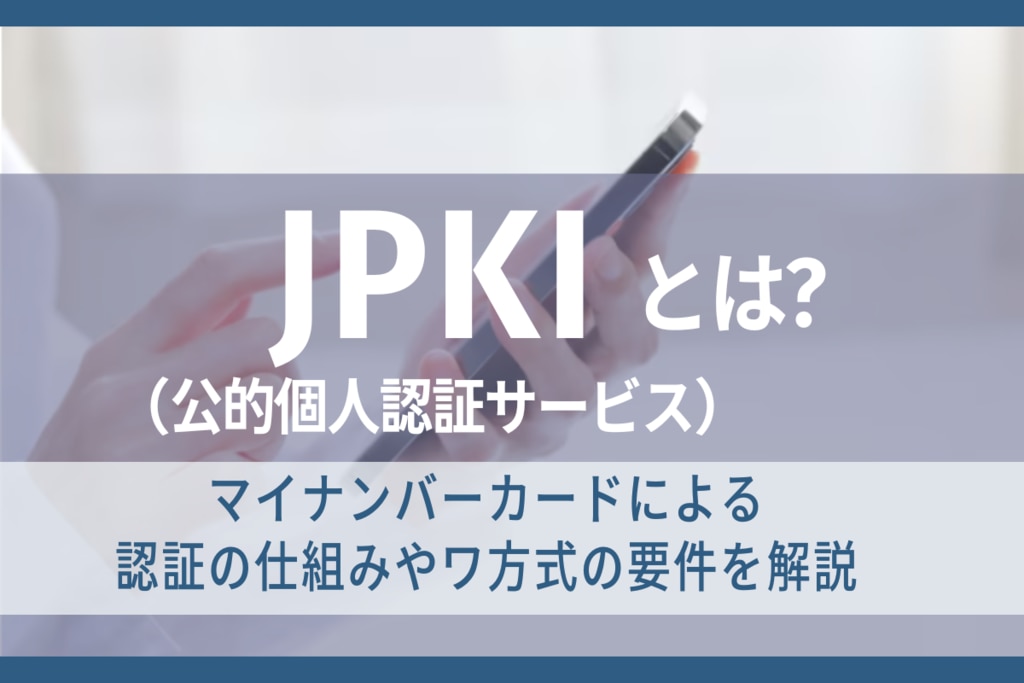
JPKIとはマイナンバーカードに搭載されているICチップに保存された電子証明書を利用する公的個人認証サービスです。顧客との取引時に金融機関や特定業者に本人確認を義務付けている犯罪収益移転防止法(犯収法)において、ホ、ヘ、ト、ワ、チという5つの本人確認手法が定められており、JPKIはワ方式に該当します。
本項では、JPKIの要件であるワ方式について解説するとともにJPKIとeKYCとの関係や、現在における本人確認手法の主流であるホ方式からワ方式に本人確認手法の移行が進められていることについて解説します。
マイナンバーカード機能のスマホ搭載についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
マイナンバーカード機能のスマホ搭載とは?申し込み方法や安全性について解説
JPKI(公的個人認証サービス)を活用したワ方式とは
前項で少し説明したように、犯収法の条項では、JPKI(公的個人認証サービス)を活用した本人確認手法を「ワ」方式として定めています。
「ワ」方式では、マイナンバーカードに記録される2種類の電子証明書のうち、署名用電子証明書を利用します。ICチップに付与された電子証明書をスマートフォンで読み取り、事前に設定したPINコード(暗証番号)の入力も必要です。
その後、JPKI(公的個人認証サービス)を通じてオンライン本人確認を完了させます。電子証明書という安全性が高い技術を利用するため、他人によるなりすまし・不正利用の防止が期待できます。
マイナンバーカードを使用した公的個人認証/JPKI(ワ方式)にも対応!
eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード
マイナンバーカード(IC認証)の導入方法を知りたい方は
マイナンバーカード(IC認証)導入完全ガイドをダウンロード
JPKIとeKYC(オンライン本人確認)との関係
eKYCとは「electronic Know Your Customer」の略で、オンラインで本人確認が完結する仕組みです。JPKI(公的個人認証サービス)は、eKYC(オンライン本人確認)を提供する手法のうちの一つという関係性にあります。
eKYCの詳細を知りたい方は、以下の記事もあわせてご参照ください。
オンライン本人確認eKYCとは?KYCとの違いや導入するメリットを解説
eKYCでは、「身元確認」と「当人認証」という2つの項目で本人確認をします。
「身元確認」はマイナンバーカードや運転免許証といった公的身分証により、氏名・住所・生年月日などの個人情報を確認する方法です。
「当人認証」は、ID・パスワードや生体認証により、システム認証を行っている人物が本人であることを確認します。
eKYCは、主に「ホ」方式・「ヘ」方式・「ト」方式・「チ」方式・「ワ」方式という5種類の手続要件が代表的です。
それぞれの違いは以下のとおりです。
「ホ」方式 | 「ヘ」方式 | 「ト」方式 | 「チ」方式 | 「ワ」方式 | |
確認方法 | ・顔画像 | ・顔画像 | ・本人確認書類の画像またはICチップ情報 | ・本人確認書類の画像またはICチップ情報読み取り | ・ICチップ情報(署名用電子証明書) |
安全性 | △ | 〇 | △ | △ | 〇 |
確認業務の | △ | 〇 | △ | △ | 〇 |
「ホ」方式は、顔写真と写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)を送信する手法です。本人確認書類は、表面・裏面と厚みを撮影し、書類の真正性を確認します。さらに、写真付き本人確認書類と顔写真の一致を目視により確認しなければなりません。
「ヘ」方式は、顔写真とICチップ情報を送信する手法です。マイナンバーカードや運転免許証のICチップには、氏名・住所・生年月日などの個人情報が保存されており、NFC対応スマートフォンで読み取ります。
「ト」方式は、本人確認書類の画像またはICチップ情報の送信を受け、金融機関などの特定の事業者から顧客情報の提供を受ける手法です。顧客情報を取得するため、金融機関との連携が必要です。
「チ」方式は、本人確認書類の画像を撮影して送信するか、あるいはICチップの情報を読み取り、容貌確認の代わりに転送不要郵便を送付する手法です。容貌確認に抵抗がある、カメラが起動しないといった場合にも本人確認ができ、離脱を防止できます。
「ワ」方式は、マイナンバーカードのICチップに記録された署名用電子証明書と、電子証明書発行時に設定した暗証番号を使うもので、JPKI(公的個人認証サービス)を利用した手法です。
eKYCの方式について詳細を知りたい方は、以下の記事もあわせてご参照ください。
【5選】オンライン本人確認「eKYC」にはどのような方式がある?まとめて解説!
eKYCの詳細を知りたい方は、以下の記事もあわせてご参照ください。
オンライン本人確認eKYCとは?KYCとの違いや導入するメリットを解説
ホ方式からワ方式への移行が進められている
警察庁はインターネットバンキングなどの本人確認を、2027年4月からマイナンバーカードのICチップに保存された電子証明書を読み取るワ方式に原則一本化するという方針を示しています。
現在、セルフィーと写真付き本人確認書類の撮影を使用するホ方式の本人確認が主流ですが、今後はJPKIを使用したワ方式への移行が進められることになります。
一部の金融機関では、既にワ方式を使用した本人確認の導入を進めており、マイナンバーカードを持っていない場合は、運転免許証やパスポートのICチップを読み取る方法なども用意しています。今後のオンライン本人確認は、ワ方式を使用した本人確認が主流になる予定です。
eKYCのホ方式廃止についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
eKYCのホ方式廃止で本人確認はどう変わる?今準備すべきこととは
JPKI(公的個人認証サービス)導入が進む理由
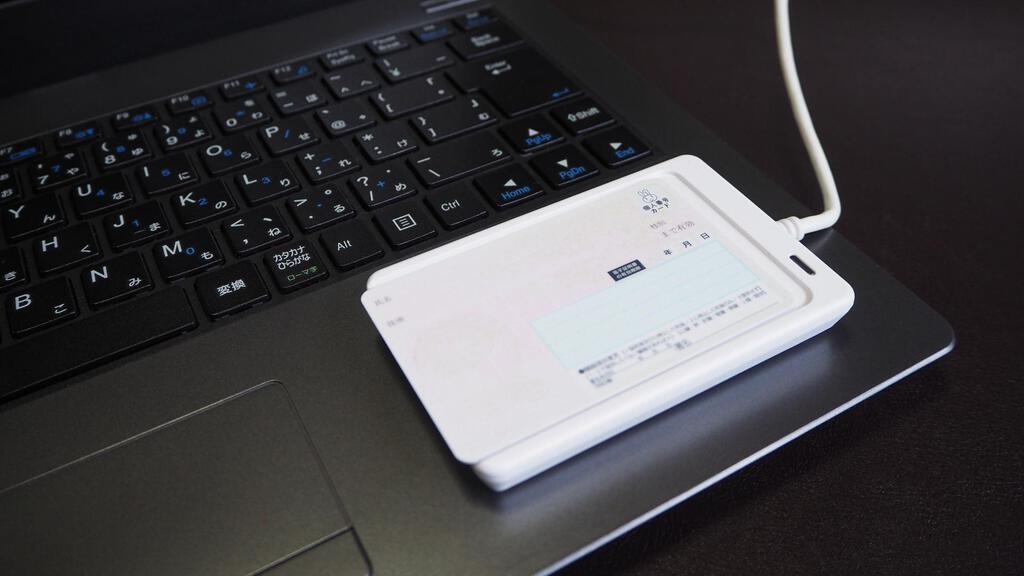
公的個人認証/JPKI(ワ方式)の導入が進む最大の理由は、2027年4月に予定されている犯収法の改正が適用されることにより、金融機関などの特定業者が実施する本人確認方式が、原則としてワ方式に一本化されるためです。
しかし、JPKI導入が進む理由は他にもあります。本項では、JPKI導入が進む理由として、国が推奨しているため民間利用が進んでいること、マイナンバーカードの普及で需要が高まっていることなどを解説します。
国が推奨し、民間利用が進むJPKI(公的個人認証サービス)
JPKI(公的個人認証サービス)は、国が行うデジタル社会実現に向けた取り組みの一環として、推奨されています。JPKI(公的個人認証サービス)の推進に向けたこれまでの動きは以下の通りです。
取り組み | 内容 |
■2023年6月開催 | 犯収法および携帯電話利用不正防止法での身元確認では「ホ」方式を廃止&「ワ」方式に原則一本化する方針が示される |
■同年6月9日 | 3本柱の1つ「カードの機能向上」内でも、公的個人認証への一本化が明記される |
■犯罪収益移転防止法改正案についてのパブリックコメントを募集開始 | 2027年3月末でホ方式が廃止になることを前提に警察庁からパブリックコメントの募集が始まる |
国はデジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選べる社会を目指しており、その基盤となるのがマイナンバー制度です。
マイナンバー制度はJPKI(公的個人認証サービス)を通して行政手続きの効率化や国民の利便性向上に役立てられ、急速に発展してきました。
マイナンバーカードの普及や利用拡大に向けた取り組みは政府全体で強力に推進されており、JPKI(公的個人認証サービス)もその一つです。行政機関で利用するだけでなく、民間事業者の各種サービスへの導入・利用が推進されています。
公的個人認証サービスのポータルサイトも設置されており、サービスの詳細を確認できます。
マイナンバーカードの今後の動向については、以下の記事もあわせてご参照ください。
マイナンバーカードの今後の動向は?現在の普及率や本人確認における懸念点を解説
デジタル認証アプリについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
デジタル認証アプリとは?概要やメリット、利用手順を解説
マイナンバーカードの普及で需要が高まっている
政府の取り組みによって、多くの人がマイナンバーカードを所有しています。その結果、JPKI(公的個人認証サービス)の民間利用が進んでいます。特に、住宅ローンの契約手続きや証券口座開設などの場面で多くの企業が活用を開始しており、2024年8月現在で580社に及ぶ状況です。
普及率においても2025年1月末に人口に対する保有枚数率が77.6%を超えており、16歳以上の人口に占める運転免許保有者数の割合である75%を超える保有率となりました。マイナンバーカードは運転免許証や保険証としても使えるようになり、今後ますます利用の需要が高まることが予想されます。
また政府は2024年6月、犯罪対策閣僚会議を開催し、携帯電話契約時のマイナンバーカードによる本人確認の強化などを決めています。携帯電話などの契約時に行う本人確認で、本人確認書類の偽造による不正契約などが相次いでいるためです。偽造書類の目視確認のミスによる、電話番号の乗っ取りなども発生しています。
強化の内容は、携帯電話契約時の本人確認において、非対面(オンライン)の場合は、原則として、JPKI(公的個人認証サービス)に一本化するというものです。店頭など対面で契約する場合も、マイナンバーカードなどのICチップ読み取りが義務化されています。そのためデジタル庁では、2024年8月20日、ICチップを読み取る「マイナンバーカード対面確認アプリ」をリリースしました。
マイナンバーカードの現在の普及率について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご参照ください。
マイナンバーカードの現在の普及率は?今後の動向や携行率も解説
マイナンバーカードによるeKYCの安全性については、以下の記事もあわせてご参照ください。
マイナンバーカードによるeKYCの安全性とは?メリット・デメリットも紹介
公的個人認証サービスの機能が拡充された
デジタル庁では、2023年、公的個人認証サービスの機能を拡充し、利用者情報(4情報)提供サービスを開始しました。
公的個人認証サービスを使って事前に本人から同意を受けていることを前提とし、顧客の最新の4情報(住所・氏名・生年月日・性別)を、J-LISにいつでもオンラインで照会できるようにするサービスです。
これまで、金融機関等事業者は、顧客情報の変更を確認するため、およそ1年に1度郵送で顧客に確認し、顧客情報を最新化しなければなりませんでした。
しかし、サービス機能の拡充により、事業者はいつでもオンラインで顧客情報を確認でき、情報を更新することが可能です。
さらに、マイナンバーカードの電子証明書の機能をスマートフォンに搭載できるサービスも開始されました。マイナンバーカードの保有者は、マイナポータルアプリから申込みができます。
これにより、マイナンバーカードを持ち歩く必要がなく、スマートフォン一つでさまざまなマイナンバーカード関連サービスの申込み・利用ができるようになりました。
なりすましや身分証偽造ビジネスが横行している
JPKIの導入が進む理由として、なりすましや身分証偽造ビジネスが横行していることも挙げられます。近年、匿名・流動型犯罪グループ(匿流)がSNSを通じて闇バイトを募集し、特殊詐欺や強盗などを行うことが社会問題となっています。匿流の犯罪活動を支えているのが、技術の発展に伴い高度化した身分証の偽造技術です。
偽造技術を用いて、なりすましや身分証を偽造しアリバイを斡旋する会社が乱立しており、大手企業の社員になりすませるよう、社員証や保険証、源泉徴収票を偽造するといった犯罪が横行しています。証明書類の偽造技術が発展し続ける中で、従来のセルフィーと写真付本人確認書類の撮影を使用するホ方式の本人確認は認証精度に限界が生じており、JPKIの導入が進む理由のひとつとなっています。
参考:産経新聞「「アリバイ会社」サイト乱立 ニセ身分証作成や在籍確認対応… 犯罪助長ツール提供」
参考:時事通信「入居審査用の保険証偽造容疑 「アリバイ会社」の幹部ら3人逮捕―警視庁」
なりすましについて具体的な種類や対策などを知りたい方は、以下の記事もあわせてご参照ください。
【事例あり】なりすましとは?代表的な手口や具体的な種類から対策まで解説
マイナンバーカードを使用した公的個人認証/JPKI(ワ方式)にも対応!
eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード
マイナンバーカード(IC認証)の導入方法を知りたい方は
マイナンバーカード(IC認証)導入完全ガイドをダウンロード
JPKI(公的個人認証サービス)を利用するメリット

自社の本人確認業務でJPKI(公的個人認証サービス)を利用することで、以下のようなメリットを得られます。
ここでは、JPKI(公的個人認証サービス)を利用するメリットを紹介します。
目視チェック不要で事務コストを削減
JPKI(公的個人認証サービス)を利用すると、オンライン上で本人確認でき、従来のような本人確認書類の受付や審査、顧客への通知といった本人確認に伴う煩雑な業務を削減できます。
一例として、銀行口座開設時の本人確認では、本人確認書類と申込書の受付・審査を行い、記入不備があれば書類の再送付を依頼しなければなりませんでした。
eKYC(オンライン本人確認)の中でも、「ホ」方式や「ト」方式では目視によるチェックで確認作業に手間がかかります。
JPKI(公的個人認証サービス)であれば、本人確認書類や顔写真の撮影が不要であり、目視チェックの必要がありません。確認業務の負担を大幅に軽減でき、人件費の削減につながります。書類の郵送や、本人確認書類の保管に伴う手間とコストも削減できるでしょう。
電子証明書による高い秘匿性
JPKI(公的個人認証サービス)で利用する電子証明書は公開鍵暗号方式という暗号化技術が用いられ、高い秘匿性があることもメリットです。
公開鍵暗号方式は、暗号化と復号に秘密鍵・公開鍵という異なる鍵を使います。秘密鍵と公開鍵は対になり、公開鍵で暗号化したものは秘密鍵でしか復号できない仕組みです。
さらに、マイナンバーカードはICチップ内の記録情報が不正に読み出されたり、解析されたりしようとした場合、自動的に内容が消去されるといった対抗措置が講じられます。そのため、秘密鍵が詐取されるというリスクはありません。
また、マイナンバーカードは、落としても他人が使えない仕組みです。顔写真付きで対面での悪用が困難であり、オンライン上のサービスを利用する場合は暗証番号が必要です。一定回数間違えると、機能がロックされる仕様になっています。
マイナンバーカードもしくは搭載したスマートフォンを紛失した場合は、コールセンターで一時停止依頼を24時間365日受け付けています。
ユーザーの利便性を高める
JPKI(公的個人認証サービス)は、ユーザーの利便性を高めるというメリットもあります。ユーザーは、本人確認書類の用意や顔写真の撮影をする必要がなく、スマートフォンとマイナンバーカードを手元に用意するだけで、オンラインからスピーディに本人確認が完了できます。
顧客情報は署名用電子証明書に記録される住所・氏名・生年月日・性別の4情報を取得できるため、ユーザーは入力の手間がかからず、入力ミスも防げます。顔写真の撮影が不鮮明で審査に通らないといった問題もありません。
利便性を高めることで、顧客満足度も向上するでしょう。
マイナンバーカードを使用した公的個人認証/JPKI(ワ方式)にも対応!
eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード
マイナンバーカード(IC認証)の導入方法を知りたい方は
マイナンバーカード(IC認証)導入完全ガイドをダウンロード
JPKIで利用する電子証明書とは

JPKI(公的個人認証サービス)における本人確認は、マイナンバーカードのICチップに記録されている2つの電子証明書で行います。
ここでは、電子証明書の詳細についてそれぞれみていきましょう。
マイナンバーカードには2種類の電子証明書が記載されている
マイナンバーカードには「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」という2種類の電子証明書が搭載されています。
電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するものです。書面取引で必要とされる印鑑証明書にあたるとされています。
マイナンバーカードに搭載されている2種類の電子証明書のうち、「署名用電子証明書」とは、マイナンバーカードを使ってインターネット等で電子文書を作成・送信する際に、文書が改ざんされていないかを確認できる証明書です。たとえば、e-Taxの利用や電子契約書の作成で利用されます。
もう一つの利用者証明用電子証明書は、インターネットのWebサイトやオンラインサービスなどにログインする際、利用者本人であることを証明する電子証明書です。たとえば、マイナポータルへのログインや、コンビニのキオスク端末で住民票の写し等を入手する際に使われます。
公的個人認証局について詳細を知りたい方は、以下の記事もあわせてご参照ください。
公的個人認証局とは?マイナンバーカードを利用したeKYCについても解説
電子署名との違い
電子証明書は、電子署名とは異なります。電子署名とは「電磁的記録(電子ファイル)」に付与される電子的なデータであり、紙の文書における印影や署名に相当するものです。付与することで、電子文書に同意したことになります。
一方、電子証明書は、電子署名そのものの正当性を証明するものです。電子証明書によって、電子署名が本人によりなされたことを証明します。
電子証明書は第三者機関である認証局によって認証されるのに対し、電子署名を証明するのは電子文書を作成した本人です。
そのため電子署名を行っても、本人の電子証明書がなければ電子文書の正当性は証明されません。
電子証明書の注意点
マイナンバーカードのICチップに格納されている電子証明書を使用したJPKIの活用が進むことで、今後はさまざまなサービスやシステムが安全で簡単に本人確認ができるようになります。
しかし、電子証明書の利用は生活を便利にできる反面、使用には注意が必要です。本項では、電子証明書を使用する際の注意点について解説します。
利用者は暗証番号を覚える必要がある
電子証明書を利用する際の注意点として、利用者は暗証番号を覚える必要がある点には注意が必要です。JPKIの利用時には、マイナンバーカードのICチップに格納されている電子証明書を読み取る必要があります。電子証明書の読み取り時には4桁の暗証番号が必要です。
暗証番号は電子証明書の発行手続きを市区町村で行った際に、窓口の案内に従って登録しており、署名用電子証明書には6桁から16桁の英数字、利用者証明用電子証明書には4桁の数字を登録します。
電子証明書発行時に登録した暗証番号がわからないと、JPKIの認証や署名が利用できなくなり、暗証番号の入力を規定回数以上誤るとロックがかかってしまいます。暗証番号の登録時には各市町村の窓口で行う必要がありますが、暗証番号のロックがかかってしまった際の解除については、コンビニに設置してあるキオスク端末からでも解除が可能です。
電子証明書には有効期限が存在する
電子証明書は利用登録をすることで使用できますが、電子証明書には有効期限が存在することには注意が必要です。マイナンバーカードには署名用電子証明書及び、利用者証明用電子証明書を格納することができますが、それぞれ電子証明書の発行から5回目の誕生日までという有効期限が定められています。
また、マイナンバーカード自体にも有効期限が存在し、発行時に18歳以上の場合はカード発行から10回目の誕生日までとなります。
各電子証明書またはマイナンバーカードの有効期限が切れると電子証明書は利用できなくなるため、注意が必要です。電子証明書及びマイナンバーカードの有効期限が近づくと、2ヶ月から3ヶ月前を目処に地方公共団体情報システム機構より有効期限を通知する書類が届くため、忘れずに更新手続きを行いましょう。
マイナンバーカードを使用した公的個人認証/JPKI(ワ方式)にも対応!
eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード
マイナンバーカード(IC認証)の導入方法を知りたい方は
マイナンバーカード(IC認証)導入完全ガイドをダウンロード
民間事業者がJPKI(公的個人認証サービス)を導入する方法

民間事業者がJPKI(公的個人認証サービス)を導入する場合は、以下の2つの方法があります。
それぞれの方法について、詳細についてみていきましょう。
認定事業者になる
電子証明書の有効性をJPKI(公的個人認証サービス)が提供するJ-LISへ確認するためには、システムを整備し、主務大臣(内閣総理大臣および総務大臣)の認定を受けなければなりません。認定を受けた民間事業者は「プラットフォーム事業者(以後、PF業者)」と呼ばれます。
PF事業者になると、電子証明書による本人確認を他の民間事業者に提供することが可能です。
PF事業者になるための手続きは、以下の手順で進めます。
サービス導入の認定を受けるためには、8個の評価項目からなる認定基準を満たす必要があります。認定審査の審査方法は、基本的に書類審査と現地調査が行われます。
認定取得後の動作確認が正常に行われ、本番環境で動作確認に問題がなければ、サービスの利用を開始するという流れです。
参考:デジタル庁「公的個人認証サービス利用のための 民間事業者向けガイドライン」
認定事業者に署名検証業務を委託する
民間事業者がJPKI(公的個人認証サービス)を導入するもう一つの方法は、認定を受けた事業者に公的個人認証を活用したeKYC(オンライン本人確認)サービスを委託することです。これにより、各事業者は認証を受けなくとも、公的個人認証サービスを導入できます。
委託により公的個人認証サービスを提供する事業者を「サービス提供事業者」と呼びます。委託することで、設備投資やシステム開発の必要なく、運用にかかる費用を軽減でき、迅速にサービスを導入できることがメリットです。
一般的に、サービス利用にはサービス提供事業者が定める利用料金の支払いが必要になり、価格は事業者によって異なります。
マイナンバーカードを使用した公的個人認証/JPKI(ワ方式)にも対応!
eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード
マイナンバーカード(IC認証)の導入方法を知りたい方は
マイナンバーカード(IC認証)導入完全ガイドをダウンロード
公的個人認証/JPKI(ワ方式)を使った認証方法
デジタル認証アプリ | ワ(アプリ) | ヘ | ||
事業者 | コスト | ⚪︎ | ⚪︎ | △ |
開発難易度 | △ | ⚪︎ | △ | |
開発自由度 | × | ⚪︎ | ⚪︎ | |
サポート | × | ◎ | ◎ | |
法令対応 | ⚪︎ | ◎ | ◎ | |
その他 | 認可の待ち時間必要 | |||
エンドユーザー | 操作性 | △ | ◎ | ◎ |
パスワード | 4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書)必要 | 6桁〜16桁のPW | 生年月日+4桁のPW | |
セキュリティ | ⚪︎ | ⚪︎ | 顔画像確認も |
2025年5月22日現在、公的個人認証/JPKI(ワ方式)を使った認証方法は、現在デジタル庁が提供するデジタル認証アプリを使用する方法と、Androidスマートフォンに搭載する方法が利用可能です。
iPhoneにもマイナンバーカード機能の搭載が予定されており、2025年3月14日にデジタル庁はコンビニでの利用を想定したデモンストレーションを公開しています。本項では、デジタル認証アプリを使用した認証方式と、スマホJPKIについて解説します。
デジタル認証アプリ
デジタル認証アプリとは、マイナンバーカードを使用した認証や署名を安全・簡単に行えるデジタル庁が提供するアプリです。デジタル認証アプリと連携するデジタル認証アプリサービスAPIを活用することで、さまざまなサービスやシステムにマイナンバーカードを使用した本人確認や認証機能、各種電子申請書への署名機能を実装できるようになります。
デジタル認証アプリは認証や署名の機能を提供していますが、アプリ単体では認証や署名はできません。デジタル認証アプリと連携しているサービスやシステムの画面にて認証を求められた際にデジタル認証アプリ上で認証や署名を行うと、サービスやシステムの画面に認証や署名の結果が反映される仕組みになっています。
デジタル認証アプリについて概要やメリットなどを知りたい方は、以下の記事もあわせてご参照ください。
デジタル認証アプリとは?概要やメリット、利用手順を解説
スマホJPKI
マイナンバーカード保有者は、マイナンバーカードで利用できるサービスをスマートフォンだけで完結できるようになるスマホJPKIを利用できます。マイナポータルアプリよりスマートフォンにスマホ用電子証明書の搭載手続きを行うことで利用できますが、2025年5月22日時点ではAndroidスマートフォンのみで利用可能です。iOSスマートフォンについては2025年春の終わり頃に利用開始を予定しており、準備が進められています。
スマホJPKIを使用することでスマートフォン1つで、マイナポータルやコンビニ交付サービスなどの利用ができるようになります。提供サービスは今後も拡大予定で健康保険証としての利用ができるようになる見込みです。
マイナンバーカード機能のスマホ搭載について申し込み方法や安全性について知りたい方は、以下の記事もあわせてご参照ください。
マイナンバーカード機能のスマホ搭載とは?申し込み方法や安全性について解説
マイナンバーカードを使用した公的個人認証/JPKI(ワ方式)にも対応!
eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード
マイナンバーカード(IC認証)の導入方法を知りたい方は
マイナンバーカード(IC認証)導入完全ガイドをダウンロード
ネクスウェイが考える現時点の本人確認の最適解

警察庁が発表している通り、2027年4月より犯収法が適用される金融機関などの特定業者が実施する本人確認方式はワ方式に原則一本化されるため、今後は公的個人認証を使用した本人確認が主流になることが見込まれます。
しかし、公的個人認証も導入には準備が必要なため、時間をかけて計画的に導入する必要があります。そのため、本項ではネクスウェイが考える現時点での本人確認の最適解として、「ホ」方式と公的個人認証を併用しながら、世の中の流れに合わせて公的個人認証に一本化していくことについて解説します。
ホ方式は継続的に利用
今後、本人確認方式は2027年4月に新しい犯収法が適用されることで公的個人認証/JPKI(ワ方式)を使用したワ方式に原則一本化されますが、それまでは現在主流となっているホ方式についても継続的に利用できます。
今後は公的個人認証を使用したワ方式が主流になることが予想されるものの、現時点では電子証明書のパスワードを忘れてしまい利用できない方や、マイナンバーカードを所有していないなどの理由で、公的個人認証/JPKI(ワ方式)が利用できない方も一定数いることでしょう。
そのため、公的個人認証/JPKI(ワ方式)に完全に一本化するのではなく、現在主流となっているホ方式を継続して利用し、公的個人認証をあわせて導入することがおすすめです。そうすることで、ユーザーの取りこぼしを最小限に抑えられるでしょう。
従量課金サービスを利用することで様子を見て切り替えていく
ホ方式とあわせて公的個人認証/JPKI(ワ方式)を導入する際は、従量課金で導入することで導入コストを抑えられます。
ホ方式の利用率と公的個人認証/JPKI(ワ方式)の利用率やコストのバランスを継続して確認していきながら、世の中の流れに合わせて一本化に対応していくことがおすすめです。
また、同一サービスでホ方式と公的個人認証/JPKI(ワ方式)を導入しておくことで、今後と公的個人認証/JPKI(ワ方式)に一本化された際のシステム的な切り替えを容易に行えるようになるでしょう。
マイナンバーカードを使用した公的個人認証/JPKI(ワ方式)にも対応!
eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード
マイナンバーカード(IC認証)の導入方法を知りたい方は
マイナンバーカード(IC認証)導入完全ガイドをダウンロード
JPKIを活用する「ワ」方式も提供するネクスウェイの本人確認ソリューション

JPKI(公的個人認証サービス)の導入を検討する際は、「ネクスウェイの本人確認ソリューション」がおすすめです。
前述の通り、JPKI(公的個人認証サービス)を活用する「ワ」方式には多くのメリットがありますが、マイナンバーカード自体や、ICチップを読み取る端末を持っていないユーザーに対応できない、ということになってしまいます。
ここでは、JPKIを利用できるネクスウェイの本人確認ソリューションを紹介します。
「ワ」方式以外の手法も利用できる
ネクスウェイの本人確認ソリューションでは、JPKIを活用する「ワ」方式も提供するだけでなく、「ワ」方式以外の手法も利用できます。
セルフィーと写真付き本人確認書類の撮影を組み合わせた認証方式であるホ方式や、セルフィーと写真付本人確認書類のIC情報を組み合わせた認証方式であるへ方式などワ方式以外の認証方式にも対応しています。
さまざまな認証方式を組み合わせることで、公的個人認証を利用できないサービス利用者などの取りこぼしを防げます。
従量課金制のためコストを抑えられる
一般的に、本人確認ソリューションを導入する際には次のような費用がかかります。
このほか、OCR機能やBPOサービス、反社チェックなどオプションを選ぶ場合、別途費用がかかります。
ネクスウェイの本人確認ソリューションは、毎月の利用件数に応じた従量課金制です。固定費ではなく変動費として利用でき、利用者数の増減にもフレキシブルに対応でき、コストを抑えられます。
→ネクスウェイの本人確認ソリューションの料金表を無料でダウンロード
さまざまなシーンで利用されている
ネクスウェイの本人確認ソリューションは、クレジットカード発行時やマッチングサービス登録時など、本人確認が必要になるさまざまなシーンで活用されています。
ここからは、ネクスウェイの本人確認ソリューションを活用して成功しているいくつかの事例を紹介します。
クレジットカードの発行時
クレジットカードの発行時には本人確認が行われますが、従来は窓口で提出するか、申込書にコピーを添付して郵送するといった方法がとられていました。
ユーザーにとっては手間がかかる方法であり、申請してからクレジットカードを受け取るまで日数を要するため、申込みを諦めるケースも少なくありませんでした。
近年は本人確認にeKYCが導入されたことで、オンラインから本人確認ができるようになり、手続きが手間なくスピーディに進むようになっています。
ネクスウェイの本人確認ソリューションではJPKI(公的個人認証サービス)を活用した「ワ」方式にも対応しているため、マイナンバーカードとそれに対応したスマートフォンがあればすぐに本人確認ができます。
迅速なクレジットカードの発行で、顧客満足度は向上するでしょう。
ネクスウェイの本人確認ソリューションをクレジットカード発行の本人確認で利用し、スムーズなカードの発行を実現した事例を紹介します。
ネットショップ作成サービスを運営する「BASE株式会社」は、「BASEカード」発行時の本人確認手続きを、より安全かつスピーディに行うことを検討し、ネクスウェイの本人確認ソリューションの利用を決定しました。
本人確認業務をワンストップで対応するネクスウェイのサービスから、eKYC後の本人確認書類の目視チェックなどに対応する「本人確認BPOサービス」と、本人確認書類の印刷発送、郵便追跡を行う「本人確認・発送追跡サービス」を導入することになりました。その結果、スピーディな本人確認作業と、ショップオーナーに対するスムーズな「BASEカード」の発行を実現しています。
マッチングサービスの登録時
マッチングサービスにおける本人確認は法律上の義務ではありませんが、複数登録やなりすましなどが起こると、サービスの信頼性を損ないます。そのため、リスクを防止するために本人確認ソリューションを導入する企業が増えており、オンラインで迅速に本人確認ができるeKYCには特に注目が集まっています。
ユーザーの信頼性を高めるため、ネクスウェイの本人確認ソリューションを導入したマッチングサービスの事例をみてみましょう。
健康管理やスポーツに特化したマッチングサービス「FISTY」は、その立ち上げにあたってeKYCサービスの導入を検討していました。ユーザーに、より質の⾼いマッチング体験をしいただくため、なりすましや荒らし⽬的といった利⽤者を防⽌し、サービスの信頼性を担保することが目的としています。
ネクスウェイの本人確認ソリューションを選んだ理由は、ミニマムな件数からの導⼊ができ、サービスの成⻑に伴う利⽤者の増加にも柔軟に対応できるという点が決め手になったということです。
決済サービスの申込時
決済サービスの申込みでは、なりすまし詐欺やマネーロンダリングなどの犯罪への対策として本人確認が求められます。対面や郵送による本人確認は時間がかかり、ユーザーの離脱につながるという懸念から、eKYCの導入を検討する企業が増えている状況です。
決済サービスでも、ネクスウェイの本人確認ソリューションを導入している企業は多く、その一例を紹介します。
大手企業を中心に「決済サービス」を展開してきたSBペイメントサービス株式会社では、サービスの幅を広げて個人事業主のお客様にサービスを提供することになり、安全・スピーディな本人確認フローを検討していました。なりすまし詐欺や、ペーパーカンパニーを防ぐ目的です。
その結果、eKYCから本人確認書類の目視確認・情報の突合などをワンストップで依頼できるネクスウェイの本人確認ソリューションを導入することになりました。
導入後は、個人事業主のユーザーに対するeKYCを含めた本人確認フローの型を構築できたということです。
マイナンバーカードを使用した公的個人認証/JPKI(ワ方式)にも対応!
eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード
マイナンバーカード(IC認証)の導入方法を知りたい方は
マイナンバーカード(IC認証)導入完全ガイドをダウンロード
まとめ

JPKI(公的個人認証サービス)はマイナンバーカードの普及に伴って注目を集め、導入する民間事業者も増えています。目視不要で確認業務の負担を軽減でき、ユーザーの利便性を向上して離脱を防止するという点がメリットです。顧客満足度を高められるでしょう。
また、2027年4月に新しい犯収法が適用されることで、今後は公的個人認証を使用した本人確認が主流になることが予想されます。しかし、マイナンバーカードを所有していないなどの理由で、公的個人認証/JPKI(ワ方式)が利用できない方も一定数いることが予想されます。
そのため、新しい犯収法が適用されるまでは、「ホ」方式と公的個人認証を併用しながら、世の中の流れに合わせて公的個人認証に一本化していくことが最適解であると考えます。
JPKI(公的個人認証サービス)の導入には、ネクスウェイの本人確認ソリューションがおすすめです。eKYC(オンライン本人確認)から郵便の発送追跡まで、本人確認の業務に必要な工程をワンストップでサポートしています従量課金制のため、スモールスタートで始められるのもメリットです。
マイナンバーカードを使用した公的個人認証/JPKI(ワ方式)にも対応!
eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード
マイナンバーカード(IC認証)の導入方法を知りたい方は
マイナンバーカード(IC認証)導入完全ガイドをダウンロード