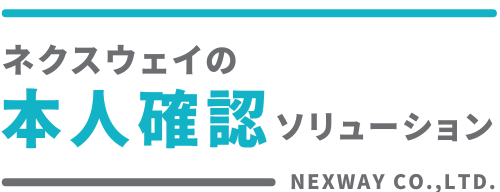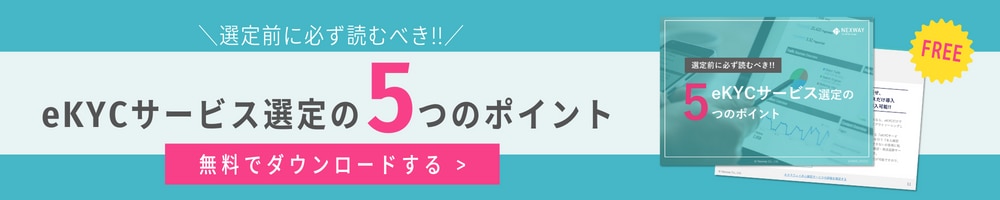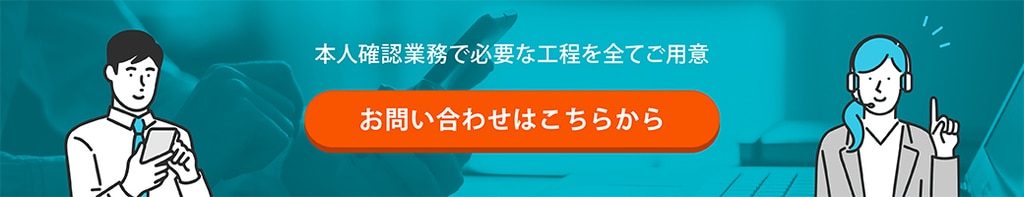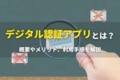有効な転売対策14選を解説!対策の事例や転売による影響も紹介
eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード
eKYC含むKYCの事例を知りたい方はKYC導入事例をダウンロード
近年、悪質な転売がニュースやネットでも大きな話題となっています。企業だけでなく、買い占めや高額転売は消費者にとっても迷惑な行為です。
しかし企業が転売対策するにはコストや労力がかかるため、対策については二の足を踏んでいるケースも多いかもしれません。結論から言えば、企業は転売対策を行うべきです。最初は転売によってそれほど影響を感じなかったとしても、長期的に見れば間違いなく大きな悪影響をもたらすでしょう。
本記事では、転売によって企業が受ける影響や転売対策について解説していきます。効果が高い転売対策としてeKYCについても詳しく言及しているので、ぜひ参考にしてください。
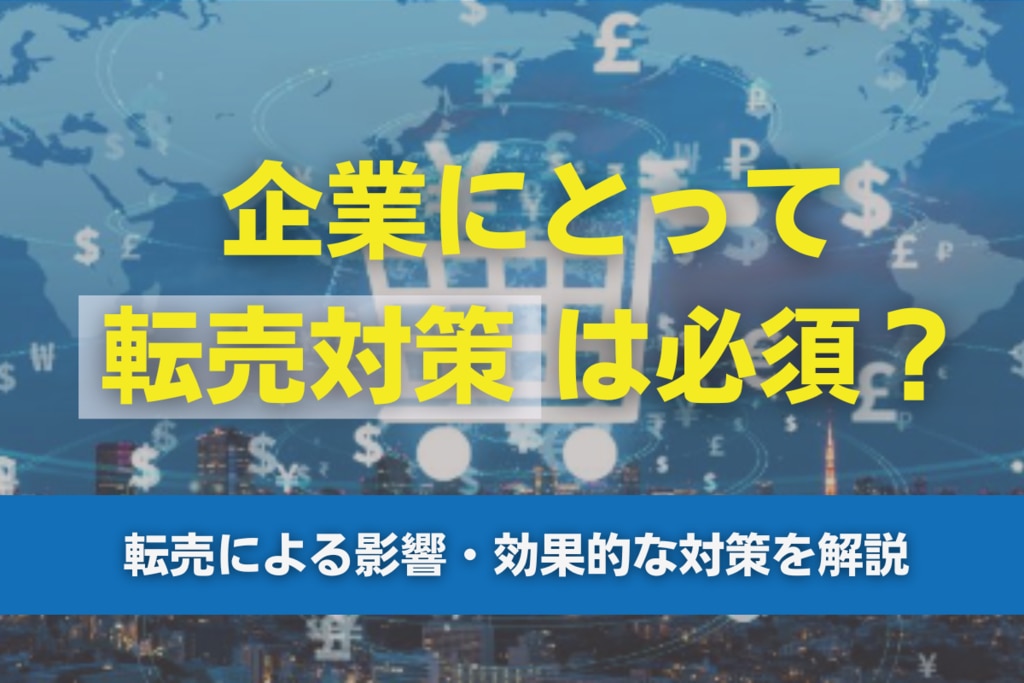
目次[非表示]
- 1.企業にとって転売対策は必須
- 2.転売者の主な種類
- 2.1.転売を副業として行っている個人
- 2.2.転売を行うための組織
- 3.転売による企業への影響
- 3.1.企業・商品イメージが低下する
- 3.2.自社商品の売上に影響する
- 3.3.転売されやすい企業と認識される
- 3.4.転売対策に労力がかかる
- 3.5.定期購入者が減り機会損失になる
- 4.有効な転売対策14選
- 4.1.1.転売者らしきユーザーを特定し購入を拒否する
- 4.2.2.整理券を配って販売する
- 4.3.3.購入できる数を限定する
- 4.4.4.外箱にマークをつける
- 4.5.5.商品の梱包を外して渡す
- 4.6.6.購入時に商品を開封させる
- 4.7.7.なりすましかどうかを確認する
- 4.8.8.購入履歴を確認してから販売する
- 4.9.9.初回購入の割引を止める
- 4.10.10.初回価格と通常価格の価格差を小さくする
- 4.11.11.申込フォームにチェックボックスを設置する
- 4.12.12.申込みの最後に転売対策の文言を追加する
- 4.13.13.アフィリエイトの審査基準を上げる
- 4.14.14.転売者に販売・出品停止を依頼する
- 5.転売対策に効果的なシステム
- 6.転売対策の事例
- 6.1.抽選販売の導入
- 6.2.限定販売で注文内容をチェック
- 6.3.大量生産への取り組み
- 6.4.転売チケットの無効化
- 7.転売対策には本人確認を厳格化すべき
- 8.転売対策にお悩みならネクスウェイの本人確認ソリューションがおすすめ
- 9.まとめ
企業にとって転売対策は必須

転売とは、ある人から購入したものを、他人に売り渡す行為のことを指します。ただし、一般的に、転売という言葉は「安く仕入れて高額で販売する行為」「人気商品を買い占めて高額で販売する行為」という意味で使われることが多いようです。
転売とは本来仕入れた商品を他方へ販売することを指し、転売行為自体は犯罪ではありません。したがって、取り締まるための法律は存在しないのが現状です。ただしチケットや中古品など、転売が違法になるケースがあります。
たとえ転売によって自社の製品を本来の価格より高額で売り捌かれたとしても、訴える先がないため企業は積極的に対策を講じたり転売されないシステムを構築していくしかありません。
eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード
eKYC含むKYCの事例を知りたい方はKYC導入事例をダウンロード
転売者の主な種類
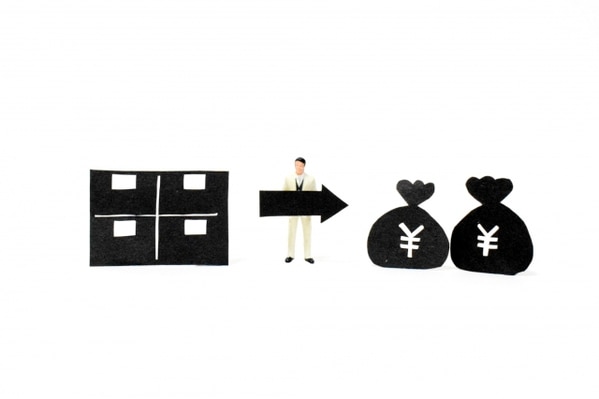
転売をする人は一般的に転売屋とも呼ばれ、大きく次のような2つの種類に分けられます。
- 転売を副業として行っている個人
- 転売を行うための組織
それぞれの特徴を解説します。
転売を副業として行っている個人
転売を行っている個人は専業として生計を立てている、あるいは副業として行っているケースが挙げられます。副業として行っているケースでは、空いた時間を活用し、収益を得るために転売活動を行っています。
転売は商品を購入する資金があれば始められ、希少価値の高い商品を手に入れれば高額で売れることもあるため、稼ぎやすい副業として選ばれることも多いでしょう。
転売を行うための組織
複数のメンバーにより組織を形成し、大規模に転売活動を行っているケースもあります。転売組織は情報網を構築しており、希少性の高い商品の情報や販売が開始される時間をいち早く入手できます。その情報を活かして限定商品を大量に購入し、高額で転売して利益を得ています。
さらに、転売マニュアルを用意し、アルバイトを雇って商品の購入と転売を繰り返し行っているケースも存在します。
eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード
eKYC含むKYCの事例を知りたい方はKYC導入事例をダウンロード
転売による企業への影響

自社製品が転売されることで、企業はさまざまな悪影響を受けます。本項目では、具体的にどのような影響を受けるのかについて解説します。
- 企業・商品イメージが低下する
- 自社商品の売上に影響する
- 転売しやすい企業と認識される
- 転売対策に労力がかかる
- 定期購入者が減り機会損失になる
それぞれの影響について詳しく見ていきましょう。
企業・商品イメージが低下する
転売屋によって商品が買い占められてしまい、買いたい消費者が買えないという状態が続くと、企業に対して不信感が募ります。なぜ転売対策をしないのかと消費者からの不満が高まるだけでなく、悪い意味で手に入りにくい商品としてイメージダウンにつながってしまうのです。
また、転売によって商品の品質を自社で担保できないこともブランド力低下の原因です。食品など消費期限がある商品の場合、転売によって期限切れや保存管理の不備で劣化を招く危険性があります。また機械類など故障時のアフターフォローや保証が必要な商品は、転売された商品には対応できません。
自社商品の売上に影響する
自社商品がキャンペーンやまとめ購入などで定価より割引価格で安く購入されたあと、定価で転売されると、本来自社で売上になるはずだった金額が大幅に損なわれることになります。
あるいは、初回限定価格などで安く購入した商品が定価より安く転売されると、本来の販売元で購入するよりも転売された商品を買う方が得だと消費者に判断される危険性もあります。結果として、やはり自社での売上は下がることになるでしょう。
転売されやすい企業と認識される
転売を繰り返していても放置して何も対策しなければ、転売しやすい企業と認識されてしまいます。転売する人に狙われやすくなると、上述したように企業や商品イメージが低下するだけではなく、被害拡大にもつながってくるでしょう。転売する業者の中には、転売しやすい企業をリスト化して情報を発信しているケースもあるようです。転売がどんなに小規模なものであっても、見かけたら即対応するべきでしょう。
転売対策に労力がかかる
転売屋かどうかを特定するには、購入者のリストを作成したり、購入履歴を一件ずつ確認したりするなどの作業が必要になります。一人で大量の数を購入したり、購入数は少なくとも頻繁に購入したりという不審な動きが見られれば転売だという判断も下しやすいですが、複数のアカウントや氏名でなりすまして購入している場合は、アカウント情報から探って検討しなければなりません。こういった作業は販売・発送などの通常業務と並行して行わなければならないため、リソースをかなり圧迫することになるでしょう。売上には貢献しない転売対策に追われるのは、労力と気力が削られてしまいます。
定期購入者が減り機会損失になる
商品を定期購入してもらうことで、通常価格より割引にして販売している事業者は少なくないでしょう。しかし、割引価格よりさらに安く転売されてしまうとユーザーは定期購入にするメリットがなくなり、販売機会の損失につながります。
eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード
eKYC含むKYCの事例を知りたい方はKYC導入事例をダウンロード
有効な転売対策14選

転売が企業にもたらす悪影響は大きいものです。転売を見つけたら即対処することはもちろん、そもそも転売されないような対策をしておくことが重要になります。
転売は主に物販やチケットなどで行われますが、ここでは、物販における転売対策として効果的な14の方法を紹介します。
チケットの転売対策についてはこちらの記事もご覧ください。
チケットの転売対策とは?転売チケットによるトラブルと具体的な対策
すぐに取り組めそうな方法から試してみてください。
1.転売者らしきユーザーを特定し購入を拒否する
自社の商品が転売されているのを発見したら、まずは転売しているユーザーを特定する必要があります。顧客の情報を確認し、不審な点がないかを確認しましょう。
明らかに一般消費者と異なる買い方をしている場合、転売屋である可能性があります。不審な動きを見つけたら、次回から購入を拒否するように設定しましょう。
疑わしいものの、すぐに転売屋と一般消費者の判断がつかない場合でも、リストにあげてチェックを継続することが転売対策の効果を上げるコツです。
2.整理券を配って販売する
店舗でゲームやソフトなど狙われやすい限定商品を販売する場合、整理券を配布することも有効な対策です。整理券がある人だけ購入できるようにすれば、大量購入ができなくなるでしょう。
ただし、整理券のシステムを知った転売屋は、アルバイトを雇って前方の位置を占めてしまうかもしれません。整理券を配るだけでなく、本人確認を行うなどの方法も合わせて行う必要があるでしょう。
3.購入できる数を限定する
ユーザーが一度に購入できる商品数を限定するのも、転売対策として効果的な方法の一つです。
転売屋側からすれば、一度に安く大量に商品を購入できれば転売の利益を得やすくなります。なりすましで複数のアカウントを作成するのも転売屋にとっては手間のかかる作業になるため、ある程度の抑止力を期待できるでしょう。
4.外箱にマークをつける
商品をそのまま転売できる状態で渡さず、外箱に油性ペンで名前を書いてもらったり「転売防止」のシールを貼ったりしてマークをつける方法も有効です。マークがあることで、商品が転売品であることが一目でわかります。マークがある商品は商品価値が下がり、販売価格が下がって転売屋が利益を出しにくくなるでしょう。
実際に、家電量販店が人気ゲームを販売する際、包装材にマークをつけて販売したケースがあります。
ただし、一般の顧客にも同じようにマークをつけて販売することになるため、抵抗を感じる方もいるでしょう。実施する場合は丁寧な説明を行い、十分な理解を得ることが大切です。
5.商品の梱包を外して渡す
商品の梱包を外して渡す方法もあります。マークをつける方法と同じく転売価値を下げられます。
ゲームを販売する家電量販店では、販売する際にゲーム機の外箱に氏名を記入してもらい、包装を外して渡すことを条件にしていたところもあります。この方法も、一般顧客に事情を説明し、納得を得る必要があるでしょう。
6.購入時に商品を開封させる
商品の転売価値を落とす方法として、梱包だけでなく、商品自体を開封する方法もあります。商品を販売する際、購入者に商品のパッケージを開封してもらい、開封済みにすることを条件にする方法です。
例えば、これまで転売が多かったポケモンカードでは、購入時にパッケージを開封させることを条件とした店舗もあります。
個数制限と併用して取り入れることで、より転売対策に効果的です。
7.なりすましかどうかを確認する
ECサイトなどの通信販売では、1人1個の個数制限をしてもアカウントを複数作成し、商品を大量購入される可能性があります。そのため、定期的になりすましのチェックが必要です。
なりすましの手口は巧妙化しており、不正入手したログインID・パスワードを利用したり、空き室住所を使って注文をしたりします。
複数アカウントと疑われる場合は、購入者に本人確認を行うなどの対策を行いましょう。SMS認証を行えば、スマホ1台につき1アカウントしか登録できないため、複数アカウント登録抑制に有効です。オンライン本人確認サービスLiteはSMS認証機能も備えています。
なりすましの代表的な手口や対策についてはこちらの記事もご覧ください。
【事例あり】なりすましの代表的な手口とは?具体的な種類から対策まで徹底解説
8.購入履歴を確認してから販売する
転売をなくすためには、購入履歴の確認が欠かせません。購入履歴を見ると、転売屋と一般消費者には購入形態に大きな違いがあります。
販売前に購入履歴を確認し、転売屋と疑われるユーザーの購入を排除できるようにしましょう。
例えば、ある家電量販店では、人気商品の販売を予約制にし、過去に購入履歴があるユーザーは購入できないことにしました。また、提携クレジットカードなど決済方法を限定し、予約時に即時決済するといった条件もつけています。
9.初回購入の割引を止める
特に食品や化粧品の単品ECサイトでは、集客のために初回購入の割引を実施している事業者は多いのではないでしょうか。
初回購入で通常価格より大きく割引していると、転売屋に狙われやすくなります。たとえ2回目以降の定期購入を条件としていても、転売屋は架空の住所などでアカウントを作成して初回購入を繰り返すこともあるでしょう。とはいえ、初回購入の割引は集客するための施策として効果的なものでもあるため、効果と転売被害の両方を考慮しなければなりません。
10.初回価格と通常価格の価格差を小さくする
初回購入の割引は集客に効果的なため、販売戦略的に続けたい場合もあるでしょう。そのようなときは、割引を止めるのではなく、初回価格と通常価格の価格差を小さくすることをおすすめします。
初回価格と通常価格の差が大きいと、転売屋に狙われやすくなるためです。価格差が小さくても消費者にとってはお得感があり、商品のアピール効果は期待できるでしょう。
ただし、転売対策と割引効果での販売数増加のどちらを優先するかの判断は会社側に委ねられます。
11.申込フォームにチェックボックスを設置する
ECサイトで申込フォームに入力する際、回答必須のチェックボックスを設けることも転売対策になります。チェックボックスにチェックを入れなければ購入できない場合、転売屋は面倒に感じ、商品購入を諦める可能性があるでしょう。
定期便への希望を確認したり、商品に期待する効果を尋ねたりする内容にすれば、商品に魅力を感じて購入しようとするユーザーは、意欲的にチェックを入れてくれるでしょう。
12.申込みの最後に転売対策の文言を追加する
申込みフォームの最後に注意書きとして、転売を認めない旨の文言を追加することも効果的です。特に副業感覚で軽い気持ちから転売している個人には、罪悪感を持たせられるため効果がでやすいでしょう。
転売対策の文言には、ユーザーが読んだことを確認するチェックボックスを設置するのがおすすめです。地道な方法ですが、チェックボックスに入力するのは一手間がかかるため転売防止につながります。
13.アフィリエイトの審査基準を上げる
アフィリエイトの制度を利用した転売への対策も必要です。アフィリエイトでは紹介する商品を自分で購入すると報酬を受け取れる「セルフバック」という制度を設けているところもあります。それを利用し、実質的に商品を安く仕入れて転売するというケースが横行しています。
アフィリエイトの広告主になっている場合は転売に悪用されることを防ぐため、審査基準を上げるなどの対策が必要になるでしょう。
14.転売者に販売・出品停止を依頼する
自社商品が転売に使用されている販売サイトやフリマサイトを調査し、プラットフォームに情報を伝えて出品を停止してもらうことも効果的です。
また、出品履歴から明らかに転売が特定できる場合は、出品者に直接連絡して出品停止を依頼する方法もあります。
調査には手間と時間がかかりますが、直接連絡して注意を入れることは相手にプレッシャーを与える効果があり、転売対策をしているという姿勢を示せます。今後の転売を抑止する効果が期待できるでしょう。
eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード
eKYC含むKYCの事例を知りたい方はKYC導入事例をダウンロード
転売対策に効果的なシステム

転売しているユーザーをチェックしている時間やリソースが取れない場合は、転売対策システムを導入しましょう。
転売対策システムには、主に次のような2つのタイプがあげられます。
- 不正検知システム
- 本人確認システム
それぞれの特徴を解説します。
不正検知システム
不正検知システムとは、ネットワーク上の不正アクセスを検知し、クレジットカードの不正利用などを事前に検知するセキュリティシステムのことです。
大規模に転売を繰り返している転売組織や転売屋の情報がデータベース化されており、転売の可能性が高い場合はアラートが発動する仕組みになっています。
ただし、不正検知システムの導入にはかなりのコストがかかるため、規模が大きくないECサイトへ導入するのはあまり現実的ではありません。
本人確認システム
本人確認システムとは、本人確認書類や顔写真などの情報により、本人であるかどうかを確認するシステムです。顔認証やSMS認証などが挙げられます。
顔認証は、人の顔がもつ情報をもとに本人確認を行うシステムです。事前に顔を登録し、写真と照らし合わせて判別します。
SMS認証は、携帯電話の電話番号にSMS(ショートメッセージサービス)を送信し、そこに記載されたコードを入力して本人確認を行うシステムです。
本人確認はサイトの規模の大小に関わらず導入しやすく、購入時に本人確認することで、なりすましや転売目的の不正購入を防止できます。不正検知システムよりもコストは低く、料金体系はシステムにより異なりますが、従量課金制であれば必要最小限のコストで利用可能です。
顔認証システムについてはこちらの記事もご覧ください。
eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード
eKYC含むKYCの事例を知りたい方はKYC導入事例をダウンロード
転売対策の事例

転売対策は多くの企業が取り組んでいます。ここでは、物販やチケット販売で行われている転売対策の事例をみていきましょう。
抽選販売の導入
家電量販店の「ノジマ」では、オンラインサイトの転売対策として、抽選販売を導入しています。先着順の販売では、特別なツールを使用している転売屋がすぐに買い占めてしまい、販売終了となるケースが少なくありません。
そのような事態を防ぐため、サイトでは抽選販売やシークレット販売を導入し、誰でも参加できるようにSNSを利用して、販売開始情報をアナウンスしています。
参考:転売撲滅宣言!ノジマオンラインでは転売目的のご注文をお断りいたします。そのため安心してお買い求めいただけます。 | ノジマオンライン
限定販売で注文内容をチェック
こちらも、ノジマのオンラインサイトにおける事例です。
転売対策として1人1個などの限定販売を実施したものの、複数注文が相次ぐことから、サイトでは複数人が目視で注文内容をチェックする作業を実施しました。転売と思われる複数購入が見つかれば、2回目以降の購入をキャンセルする作業を行っています。
また、ルールを守れない注文には、手数料を加算するというペナルティも設定しており、徹底した転売対策を講じています。
参考:転売撲滅宣言!ノジマオンラインでは転売目的のご注文をお断りいたします。そのため安心してお買い求めいただけます。 | ノジマオンライン
大量生産への取り組み
大手ゲームメーカーの任天堂では、Nintendo Switch後継機の需要に対して生産が追いつかず、買い占めや高額転売が起こるという事態が想定されています。実際に、半導体部品の不足によりNintendo Switch現行機が品薄状態になった際には、転売が多く行われていました。
生産数が少ないためにこのような事態になることを防ぐため、その後は大量生産に取り組む方針を示しています。転売対策には顧客の需要を満たせる数を生産することが最重要だと考えています。
参考:任天堂株式会社 | 第 84 期 定時株主総会 質疑応答(要旨)
転売チケットの無効化
次にご紹介するのはチケット転売の事例ですが、物販の転売対策として参考になるため紹介いたします。
大阪府のテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」では、転売目的での買い占めや転売行為によるチケット価格の高騰を防止するため、公式サイトの利用規約において、チケットの転売行為を禁じる項目を設けています。その上で、SNSなどでの販売を含むすべての転売されたチケットについて、無効化する取り組みを行いました。
さらに、転売者が悪質な転売行為を継続する場合、警察に通報することがあることをサイトで明言しています。
参考:転売されたチケットのQRコード無効化について|ユニバーサル・スタジオ・ジャパン|USJ
チケットの転売については、以下の記事で詳しく解説しているため、あわせて参考にしてください。
チケットの転売対策とは?転売チケットによるトラブルと具体的な対策
eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード
eKYC含むKYCの事例を知りたい方はKYC導入事例をダウンロード
転売対策には本人確認を厳格化すべき

今回14の対策をご紹介しましたが、最もおすすめしたい転売対策は本人確認を厳格化することです。
Web上でユーザーと非対面の取引をするECサイトでは、ユーザーの本人確認をより厳格にすることも転売対策として効果があります。
オンライン本人確認(eKYC)は、オンライン上で本人確認が完了できるシステムです。よく利用されている方法としては、身分証と容貌画像の送信を受ける方法やマイナンバーのICチップへ付与された公的認証を活用する方法があります。
eKYCはすでにチケット販売やリサイクル品の買取など多くのサービスで導入されています。スピーディに本人確認が完了するだけでなく、ユーザーの生体的特徴を利用して本人確認を行うため、なりすましなどの不正を行いにくいのもメリットです。また、犯罪収益移転防止法の要件に準じた確認手法なので、本人確認を厳格に実施したい場合に適している方法だと言えるでしょう。
購入手続きの際にeKYCで本人確認するようにすれば、転売屋の特定や複数のアカウントを作成した不正の防止に役立ちます。
eKYCについては、以下の記事で詳しく解説しているため、あわせて参考にしてください。
eKYCとは?オンライン本人確認とKYCの違いや導入するメリットを解説
eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード
eKYC含むKYCの事例を知りたい方はKYC導入事例をダウンロード
転売対策にお悩みならネクスウェイの本人確認ソリューションがおすすめ

転売対策に追われて通常業務が滞っている、どのように転売されない仕組みを作ればよいかわからないなどのお悩みがある方は、ぜひネクスウェイの本人確認ソリューションにご相談ください。オンラインショッピングにeKYCを導入することで、なりすましなどの不正や転売を抑制し、お取引の安全性を守ります。
ネクスウェイの本人確認ソリューションの料金は従量課金制を採用しているため、月50件〜の小ロットで対応が可能です。また、季節商品など月によって申込み数の変動が大きい場合でも費用が無駄になりません。事業の規模に関わらず、導入していただきやすいのもメリットです。
eKYCはすべて自動で完了するわけではなく、送信を受けた身分証と容貌写真の目視確認や書類の突合は人の目で行わなければなりません。また、eKYCに対応できないユーザーへの配慮も必要です。
ネクスウェイの本人確認ソリューションでは、このような本人確認に関わる業務をすべてアウトソーシングしていただけます。目視確認・書類の突合はBPOセンターで専門のスタッフが代行するサービスを提供しているほか、eKYCで対応できないユーザーへ郵送で本人確認を実施するサービスもオプションでご用意しているため、ワンストップで対応可能です。
また、オンライン本人確認サービスLiteであれば、必要な項目に絞った本人確認により、よりコストを抑えた導入ができます。自動判定機能によりスピーディな結果返却が可能であり、大量申込みや深夜休日にも対応できるため、ユーザの利便性も高められます。
→「ネクスウェイの本人確認ソリューション」の資料を見てみる
→「ネクスウェイの本人確認サービスLite」の資料を見てみる
まとめ

転売は企業・商品イメージの低下につながり、自社商品の売上に影響します。本当に必要とする消費者に自社の商品が届かず、転売屋ばかりが利益を得ることになります。対策を行わなければ、転売しやすい企業と認識されることにもなるでしょう。
転売対策には労力がかかることから、オンライン販売ではWeb上で本人確認が完了できるeKYCの導入もおすすめです。ネクスウェイの本人確認ソリューションであれば、eKYCをはじめとした本人確認業務をワンストップで対応します。
よりコストを抑えて導入したい方に向けて、オンライン本人確認サービスLiteも提供しています。SMS認証機能を備えているため、なりすましや複数登録の抑制に有効です。転売対策を検討している方は、ぜひご検討ください。
→「ネクスウェイの本人確認ソリューション」の資料を見てみる
→「ネクスウェイの本人確認サービスLite」の資料を見てみる
eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード
eKYC含むKYCの事例を知りたい方はKYC導入事例をダウンロード